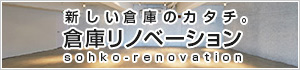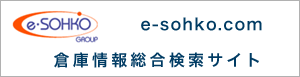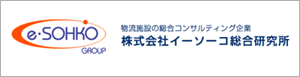資産譲渡と事業継承 succession(第7回) 物流マネー70兆円のゆくえ
物流企業経営者にとっての最大の話題は資産継承と事業の継続をどう図るかだ。
団塊世代経営者が引退を迎え、実質上の相続問題を抱えた時、次期経営者にとって事業発展のために現有資産をどのように継承するかは相続節税問題以上に悩ましい。
製造業も流通業も物流活動を必要とするために、物流施設を保有する企業は多く、更に業務委託によって物流施設を利用している。
物流事業者は最近でこそ、賃貸物件での事業を初めてはいるが、運輸倉庫ともに規制緩和前からの事業者は多くの自己資産で倉庫や物流施設を保有している。
不動産の保有は、かつては値下がりしない絶対の信用として特別な意味を持っていた。
倉庫も不動産も、それは力の象徴であり、信用の証として経営を支えてきた。
こういう時代が物流の規制緩和とバブル経済の崩壊によって失われた。その余震は未だに収まらず、もはや値上がりはしない不動産神話が形骸として残り、担保価値としてだけの不動産保有の意味は失われた。
しかし、不動産固有の特徴が今でも効力を持っていることは確かなのだ。それは、不動産がマネーを生み出す力を持つという真理だ。不動産所有が景気リスクであり、納税分だけがデメリットになった時期も確かにある。しかし、物流経営に欠かせない資源としての不動産は、所有者にも利用者にもメリットという選択肢が残されている。
問題は租税なのだ。所有であれ、相続であれ、個人企業や個人所有では重い課税が待ち受けている。節税のために別事業を控えたり、余計な設備投資を繰り返したりと様々な取り組みがなされてきた。
事業継続のために地域の倉庫、物流施設を創業者の手から守る方法がある。
それが不動産の証券化と呼ばれる手法である。不動産保有専門法人を立上げ、物流事業者や個人所有から倉庫と物流施設を切り離す。所有と利用を兼ね備えた手法であり、詳しい解説は譲るが画期的である。
地域の物流業者にとっての事業継続のソリューションとして、与えられた選択肢なのである。
<イーソーコ総合研究所 主席コンサルタント 花房 陵>