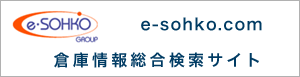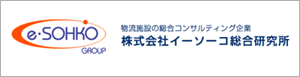カーゴ・カルト・リアルエステート
東南アジアの島々で伝統的な暮らしを営んできた人々のほとんどは、太平洋戦争によってはじめて西欧的な現代文明に触れたといわれている。連日の爆撃で地ならしされた島に巨大な揚陸艦があらわれて怪物のようなブルドーザーが上陸し、一晩にして滑走路をつくる。そしてどこからともなく輸送機が現れ、見たこともないような「すばらしいもの=便利な工業製品」をたくさん運んでくるのだ。産業革命を経験せず、現代文明の恩恵に浴することがなかった島民たちの目に、それは魔法か奇跡のように映ったことだろう。
やがて戦争が終わると、奇跡も終わる。輸送機は飛んでこなくなり、すばらしいものをたくさん持っていた白人たちは姿を消し、滑走路も荒れ果てていく。
草に覆われた飛行場を見ながら、島民たちは考えた。あのすばらしいものは神が創ったものだ。我々にも得る権利がある。これまで独占してきた白人がいなくなったのだから、今度は自分たちがすばらしいものを手にする番だ、と。
そこですばらしいものを得るための儀式として、白人たちと同じことをやってみることにした。滑走路をきれいに掃除し、木や竹で管制塔や格納庫の模造品をつくった。米軍の軍服に似た格好をして銃に似せた木の枝を持ち、「飛行場」を練り歩いた。それで何事も起こらないと、輸送機が警戒しているのかもしれないと考え、模造機をつくって滑走路に並べてみた。もちろんそんなことをしたところで、すばらしいものを積んだ輸送機など来はしない。しかし彼らはあきらめなかった。模倣が不完全だと考え、米軍の飛行場を細部まで再現することに熱中した。管制官は木で作った無線機で交信を続け、誘導員は滑走路に立ち着陸の合図を出し続けた。考え付く限り、ありとあらゆることをやってみた。やがて漁や農作業をするものは減り、村は荒れていった。これを、カーゴ・カルトという。
このカーゴ・カルトは一種の宗教と位置づけられ、さまざまな学問の研究対象ともなった。宗教的伝統行事として今も米軍の模倣を続けている島があるともいうが、昨今では「無駄なもの」や「無駄なこと」「無駄な努力」の比喩として使われることが多い。その代表例の一つが、物理学者のリチャード・ファインマンだろう。彼はある席で、「科学の本質を理解せずにその手法だけを模倣したところで、それを科学と呼ぶことはできない」とスピーチし、これを「カーゴ・カルト・サイエンス」と呼んだ。そして「それにもかかわらず、多くの科学者がこれに陥る」とし、科学が本質のないカタチだけのものになることを厳しく戒めた。
物流不動産においては、すでに物流は学問の一分野となっている。一方の不動産は、ようやく学問としてとらえようという動きがでてきたところ。それぞれの専門誌には関連する方程式や数式が載ることがあるが、その内容がちんぷんかんぷんなのは素養のない筆者の責任であって、これをカーゴ・カルト・サイエンスと呼ぶつもりは毛頭ない。
しかし、である。マンションを真似た建物を建てたところで入居者は入らないし、オフィスビルを模した建物を建ててもテナントは入らない。倉庫を模倣した建物をつくったところで、荷物は入らないのだ。
久保純一 2018.8.5