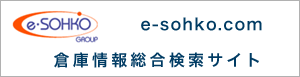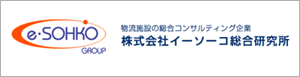調停と訴訟 − 第7回 コントラクトマネジメント(契約)
調停とは紛争当事者間に第三者が存在して、解決をすすめる制度化された手続きを言います。いわば交渉をすすめるのに第三者が調整をする作業を法律で定めているというものです。裁判所には調停を進めてゆくための事務方と呼ばれる職員がいます。双方の申し出や意見について、裁判に掛ける前段階で矛盾や異論の争点を明らかにしてくれる、双方にとっての中立的な立場で意見を述べてくれることがあります。
ADR(裁判外紛争可決手段)では国民サービスセンターの専門職員が同じような働きをしてくれますが、調停を冷静に進める、つまりは対立する利害の双方を冷静に聞き入れる人がいなければ、水掛け論というか、声がどんどん大きくなるだけです。
私たちは訴訟は必ず決着するものだ、つまり白黒がはっきりするものだという裁判の結果をイメージしがちですが、テレビ番組のように裁判官が判決を下すような、法廷決着の前段階でも常に調停作業が進むものです。
たとえば、アメリカの法廷番組では裁判官が当事者双方の弁護士を呼びつけて、司法取引をする場面が良く登場します。あの時には、検察側の弁護士と裁判官が落としどころを探っているわけです。
刑事裁判は無実か有罪かを争うものですから、調停は有罪だけれども罪の重さを交渉していることになります。民事裁判では被害の程度を金銭額で示すことになるので、調停では金額の交渉になる訳です。
民事事件での損害賠償訴訟を起こしたとします。双方にとって争うべき事実は、損害の認定とその金額が争点となったとき、対立は該当する事実があった・なかったから始まり、賠償金額の大小に及びます。そして、賠償の責任範囲や義務がそもそもあったかどうか、という業務関係の契約書の内容に及ぶわけです。
契約書の条文や項目、そして協議事項の内容や協議の記録、発言者の発言内容まで遡っていきます。調停も訴訟もこのような事実認定や争うべき金額や責任関係の事実をどうやって証明してゆくか、調停する人にどのような判断を期待するかもすべて事実の記録が必要になります。
交渉か対決か、というのが調停と訴訟の違いになるわけですが、どちらも事実認定=双方が納得する事実の証明が必要になります。事実、実際にこうだった、ああだった、という事実の確認は、意外と難儀なことなのです。
日常の作業や行為がすべて記録されていることはあり得ないし、発言や風景がすべて録音と写真で残されているわけではありません。そのような状況下で事実を確認していく作業は、想像をはるかに超える難物です。契約書が文章で書かれている以上、これは明らかに事実として認定されます。文章はそれだけで重要な価値があるのです。しかし、文章の解釈や意味、意図は双方が対立するように、事実が事実でなくなる場面もあります。「そのような意図や意味とは思わなかった」という解釈の問題は、それが認められるか、許される事なのか、紛争の原因となるわけですから、事実認定を巡る意見の対立が調停を進めることができるか、諦めて訴訟に持ち込むかの分かれ目になります。
事実をどのように解釈するか、どのように認識するか、どの範囲まで認めるか、という事実を巡る解釈が争い事の背景にあることを知らなければなりません。
たとえば、新センターへの移転と物流業者交代、新システムの稼働に伴って多額の在庫違算が発覚した事件がありました。珍しく一般紙にも扱われた家電量販店ラオックスの物流事故に関わる事件です。
物流センターの移転前後で7千万円の在庫違算が発生し、決算期をまたいでいたために企業側は決算のやり直しをしなくてはならなくなりました。家電製品という大きな荷姿の商品が千万単位で在庫が狂った事件は、原因追及に時間が掛かりました。情報システムの在庫情報が狂ったのか、商品の移転前後で在庫が紛失したのか(物理的にはあり得ませんね)、確定在庫金額で決算を行い利益が確定した後に(在庫は企業利益ですから!)、在庫金額の違算が発覚して、決算の減額申告が必要となった事実を巡り、企業側と物流受託側との責任問題が訴訟になりました。調停作業も同時に進行して、結局は35百万円の損害賠償を認めるという調停決着が行われました。このニュースが発表された時には様々な衝撃が物流業界に走ったものです。
同種の事件は表面化したことがとても珍しい、という意見と調停や訴訟にならずに現場レベルで決着することが多いのだ、という打算的な見解があって、契約書があってもなくても物流事業者は損な立ち回りをするものなのだ、という諦めムードの話題も広まりました。契約は双方平等であるべきなのに、日本では契約社会ではまだまだ幼稚なレベルにあるのだということを深く考えさせられた事件だったのです。
(イーソーコ総合研究所・主席コンサルタント 花房 陵)